前頭葉の機能低下は、判断力や社会的認知能力に影響を与え、嘘を見抜く能力を低下させる可能性があります。
前頭葉、特に前頭前野は、高次脳機能を司る重要な部位で、判断力、社会的認知、感情制御などに深く関与していて、社会的認知に関しては、前頭葉内側部が表情の認知や意図の理解に重要な役割を果たしています。
前頭葉の機能が低下するとさまざまな影響が考えられます
• 力の低下:複雑な状況を適切に評価し、正しい判断を下す能力が低下する可能性がある
• 社会的認知の障害:他者の感情や意図を正確に理解することが困難になる可能性がある
• 注意力の低下:嘘を示唆する微妙な手がかりに気づきにくくなる可能性がある
• 実行機能の低下:情報を統合し、論理的に推論する能力が低下する可能性がある
これらの要因により、前頭葉の機能低下は嘘を見抜く能力を低下させる可能性が高いと考えられますが、嘘の検出に関する脳の働きは複雑で、前頭葉以外の脳領域も関与している可能性があることに留意する必要があります。
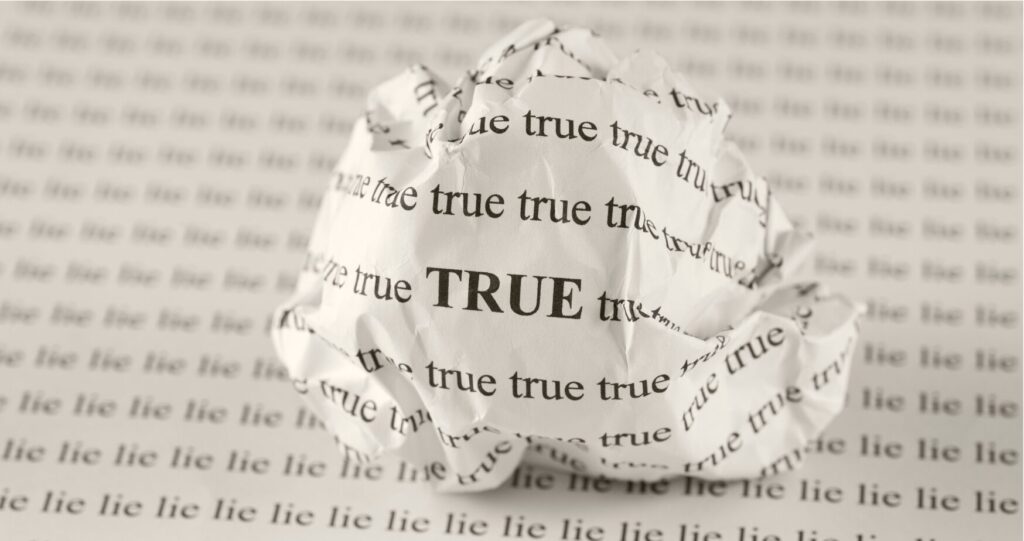
嘘をつく人の脳内は、報酬への欲求や理性の働きに関連する複数の脳領域が関与しています。
嘘をつく際の脳のメカニズム
◇側坐核
• 側坐核は「やる気スイッチ」とも呼ばれ、報酬への期待や動機づけに関与する部位です
• 京都大学の研究によれば、報酬を期待する際に側坐核が活発に働く人ほど、嘘をつく傾向が高いことが分かっていて、特に金銭的な報酬への欲求が強い場合、この傾向が顕著です
◇背外側前頭前野
• この領域は理性的な判断や行動制御を担っています
• 嘘をつかない正直な人は、この部位の活動が高いことが確認されていて、背外側前頭前野は感情や衝動をコントロールし、高次な思考を行うため重要で、人間らしい行動に深く関わっています
◇サイコパスの場合
• サイコパスのように平然と嘘をつく人々では、罪悪感や感情的な抑制が欠如しているため、脳内で異なる活動パターンが見られ、これには反社会性パーソナリティ障害との関連もあります
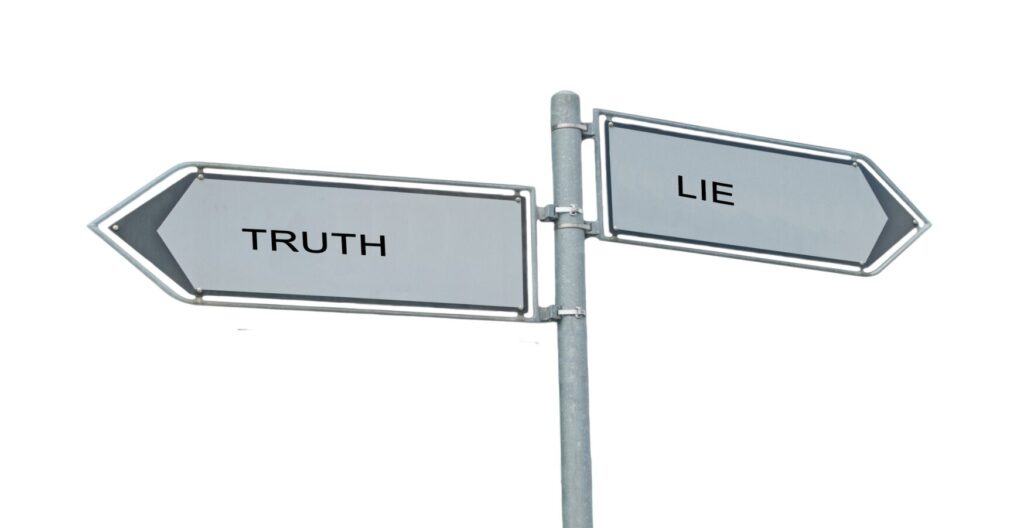
京都大学の研究では、被験者にコイントス課題や金銭報酬遅延課題を行わせ、脳活動を測定しました。
コイントス課題では、予想結果を自己申告する形式で嘘をつける状況を作り出し、その際の側坐核と背外側前頭前野の活動を比較しました。
側坐核が活発な人ほど嘘をつきやすく、理性的な判断が働いた場合は背外側前頭前野が活発になることも確認されています。
嘘をつく行為は、報酬への欲求(側坐核)と理性(背外側前頭前野)のバランスによって影響され、報酬への強い欲求がある場合、人は嘘をつきやすくなる傾向がありますが、それでも理性によって抑制される可能性があります。
この研究から、人間らしい脳の持ち主ほど正直であるという仮説も導き出されています。
前頭前野の機能を低下させる習慣
1.慢性的なストレス
• 強いストレスは、ストレスホルモンであるコルチゾールの過剰分泌を引き起こし、前頭前野の神経細胞の活動を低下させます
• ストレスが続くと、前頭前野の樹状突起が萎縮し、感情制御や集中力が低下します
2.睡眠不足
睡眠不足は脳全体の回復を妨げ、前頭前野の働きに悪影響を与え、特に注意力や意思決定能力が低下しやすくなります
3.不健康な食生活
高脂肪、高糖質、トランス脂肪酸を多く含む食事は脳に悪影響を及ぼし、前頭前野の機能低下につながる可能性があります
4.運動不足
身体活動が少ないと、脳への血流が減少し、前頭前野の働きが弱まることがあります
5.アルコールや薬物乱用
アルコールや薬物は神経伝達物質のバランスを崩し、前頭前野の機能を抑制します
6.デジタルデバイスの過剰使用
スマートフォンやパソコンなどを長時間使用することで集中力が分散され、前頭前野への負担が増加します
これらの習慣を避けることで、前頭前野の健康を維持し、高次認知機能を保つことが期待されます。



