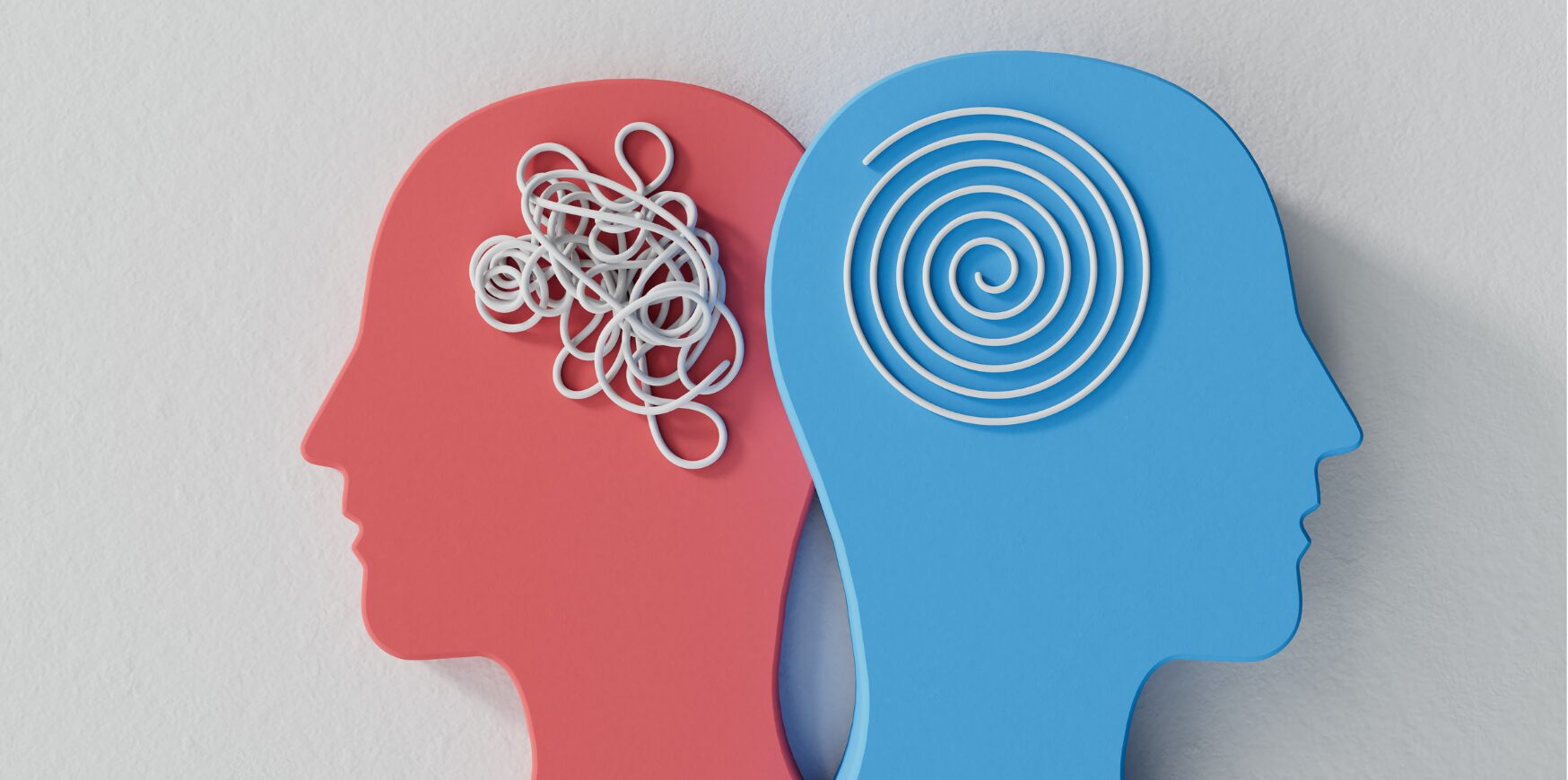腸内細菌は、セロトニン、ドーパミン、GABAなどの神経伝達物質を生成することができ、セロトニンの約90%が腸管で生成されることが知られています。
セロトニンは、「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神面の健康から消化機能まで、体全体のさまざまな機能に関与する重要な物質で不足すると、うつ病などの精神的な問題に関係してきます。
神経伝達物質は腸の神経系を通じて脳に信号を送り、脳の機能に影響を与えます。
腸内環境は免疫系にも影響を与え、間接的に脳機能に作用する可能性があり、腸内細菌のバランスが崩れると、炎症反応が引き起こされ、これが脳にも影響を及ぼす可能性があります。
この脳腸相関の概念は、近年「脳-腸-微生物相関」や「脳-腸-腸内細菌軸」という新しい概念に進化していて、精神的健康や身体的健康において重要な役割を果たすことが明らかになっています。
腸内環境に悪影響を与えるもの
• 肉類の過剰摂取は、悪玉菌のエサとなり、腸内フローラのバランスを崩す原因になり、ジャンクフードなどの高脂肪食は悪玉菌が好む典型的な食べ物
• 精製された糖質は、悪玉菌やカビ菌の格好のエサとなり、腸内環境を悪化させ、特に、果糖ブドウ糖液糖(清涼飲料水や加工食品に含まれる)は砂糖以上に腸内環境を悪化させる
• 食品添加物や人工甘味料(スクラロース、アスパルテーム、アセスルファムKなど)は腸粘膜の粘液バリアの破壊や、腸内フローラを乱す可能性がある
• アルコールは腸内細菌の働きを抑制してしまう
• 過剰な精製塩摂取は、腸内環境に悪影響を与える可能性がある

食生活を見直すことで、脳機能を向上させることができます。
適切な栄養素を含む食品を摂取することで、記憶力、集中力、思考力などの脳のパフォーマンスを高めることが可能です。
添加物の過剰摂取は脳機能の低下につながる可能性があり、特に、超加工食品に含まれる添加物が脳に悪影響を及ぼす可能性が研究によって示されていて、超加工食品を多く摂取する人は、うつ病のリスクが44%、不安障害のリスクが48%高くなることが報告されていて、摂取量が10%増えるごとに、認知症のリスクが25%上昇するという報告もあります。
添加物の影響メカニズム
• 脳内物質への干渉:人工甘味料やグルタミン酸ナトリウムなどの添加物が、ドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンといった脳内物質の機能を妨げ、精神的・感情的な満足度を低下させる可能性がある
• 慢性炎症の誘発:超加工食品に含まれる精製された塩分、糖分、飽和脂肪酸の過剰摂取は、慢性炎症を引き起こし、脳への血流を低下させる可能性がある
• 中毒性の懸念:超加工食品に含まれる添加物の組み合わせが、脳の報酬系に作用し、中毒性を引き起こす可能性がある
これらの研究結果は、添加物を多く含む超加工食品の過剰摂取が脳機能に悪影響を及ぼす可能性を示唆していて、脳の健康を維持するためには、新鮮な食材を中心とした食生活を心がけ、超加工食品の摂取を控えることが重要です。
セロトニンは、感情をコントロールする脳の前頭葉の機能を支えていて、不足すると怒りの感情のコントロールが難しくなります。
ストレスに対する耐性を高める働きがあるので不足すると、ささいなことでもストレスを感じやすくなり、気分が落ち込みやすくなったり、イライラしやすくなったりします。
健康な腸内フローラを維持することが、適切なセロトニン産生と、それに伴う精神状態の安定に寄与すると考えられています。